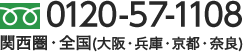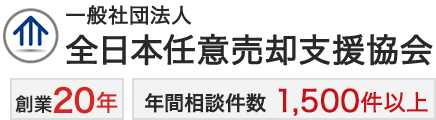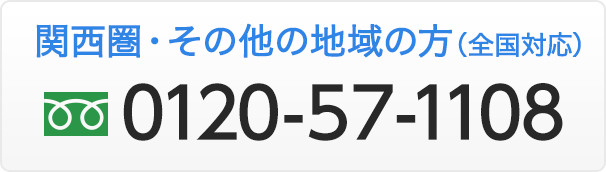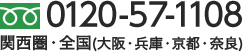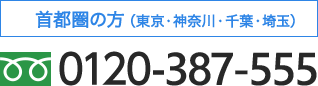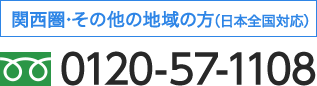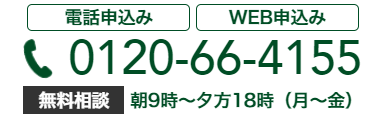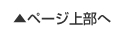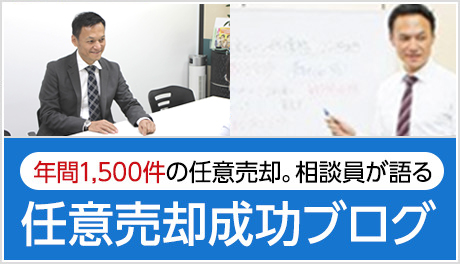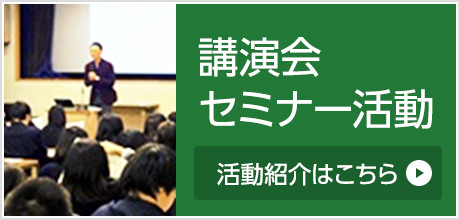住宅ローンは相続するのでしょうか?


-
この記事は私が監修しています
安田 裕次
全日本任意売却支援協会
代表理事
「住宅ローンは相続の対象になる?ならない?」と考えていませんか?
住宅ローンは相続の対象ですが、支払いを免除される場合とそうでない場合があります。
このページでは、住宅ローンが残っていて相続が発生した場合にどうするのか?について、プロが分かりやすく解説しています。
相続後、団信に加入していれば住宅ローンは免除される!
相続後、団信に加入していても免除されない5つのケースとは?
住宅ローンの団信に未加入で相続が発生した場合の3つの対応方法
住宅ローンの相続後、残債がある場合は任意売却を検討!
住宅ローンと相続についてのQ&A
相続後、団信に加入していれば住宅ローンは免除される!
団信(団体信用生命保険)に加入していると、住宅ローンは相続の対象外(免除)になります。
というのも、団信が住宅ローンを借りている金融機関に保険金を支払ってくれるため、相続するローンそのものが無くなるからです。
住宅ローンの残債は支払わなくてOKで、家はそのまま相続することができます。
これは死亡だけでなく、高度障害などによって住宅ローンを支払っていく能力を失ってしまった場合にも適用されます。
多くの場合、団信に加入していますが、まずは一度、住宅ローンを借りている銀行などの金融機関に確認してみて下さい。
なお、住宅ローンの相続手続きは相続が発生してから3ヶ月以内に行う必要があります。
具体的には「Q.住宅ローンの相続手続きは、どのタイミングで行う?」でご確認下さい。
また、相続が発生して住宅ローンが免除されるまでには10つの流れがあります。
合わせて「相続が発生して住宅ローンが免除されるまでの流れは?」で流れを把握しておいて下さい。
相続後、団信に加入していても免除されない5つのケースとは?
この5つのケースの場合、団信に加入していても住宅ローンを支払う必要があります。
詳しくご案内していきます。
【ケース①】住宅ローンの滞納
住宅ローンを3ヶ月以上滞納をすると団信との契約そのものが失効となる可能性が高いです。
団信の保険料は銀行などの住宅ローンを借りている金融機関が保険会社に支払っています。
ですが、3ヶ月以上滞納すると、代位弁済といって、銀行から保証会社に代わります。この時点(代位弁済)で団信は解約となり、保険が降りなくなります
住宅ローンの支払いが滞ったら、任意売却など、早めに手を打つようにしてください。
【ケース②】ペアローン(親子・夫婦)
ペアローンの場合、それぞれが住宅ローンの契約者となるため、亡くなった人の住宅ローンについては団信の保険金が降りますが、もう1人の契約はそのまま続くため、免除にはなりません。
例えば、親子でペアローンを組んだ場合、親が亡くなっても子の契約した分のローンは残ります。
夫婦の場合、夫が亡くなっても妻の契約した分のローンは残ります。
なお、親子リレーローンの場合は、基本的に子供側が団信に加入しますが、まれに親子での加入を求められる場合がありますので、注意が必要です。
【ケース③】加入時に健康状態について事実を告げなかった場合
これは契約違反になってしまうので、団信の保証は一切受けられなくなってしまいます。
また、故意に大けがを負った場合や、保険金目的でわざと事故を起こした場合もこれに該当します。
団信に加入したいという気持ちはわかりますが、虚偽の申告は絶対にやめましょう。
自身の信用問題にも関わってきますし、告知義務違反で住宅ローンの残債を丸ごと借金として負うことになってしまいます。
【ケース④】加入日から1年以内に自殺した場合
保障が開始されて1年以内に加入者が自殺した場合には、住宅ローンが弁済されません。
【ケース⑤】加入日前の病気や怪我・傷害が原因で所定の高度障害状態になった時
加入日の前から病気や怪我があり、それが原因で高度障害状態になった場合も住宅ローンは弁済されません。
加入時に告知していても対象にならないので、注意が必要です。
住宅ローンの団信に未加入で相続が発生した場合の3つの対応方法
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
団信に未加入だった場合の対応方法は3つあります。代位弁済代位弁済
それぞれ詳しくご案内していきます。
【方法①】単純承認
単純承認とは、家や貯金といったプラスの財産から債務などのマイナスの財産まで全て引き継ぐ方法です。
家や土地などの資産がありかつ債務がない、またはあったとしても自分の貯金+親が残した貯金で賄える場合は、この方法を選ぶのが一般的です。
逆に債務の方が大きいと損をすることになりますので、財産だけでなく住宅ローンなどの債務もきちんと把握しておくことをおすすめします。
なお、この後ご案内する「限定承認」や「相続放棄」の手続きを行わなかった場合、自動的に単純承認になります。
【方法②】限定承認
限定承認とは、残された財産からプラスになる財産の限度額まで債務を負担するという方法です。
例えば、相続が発生してから借金が多額にあることが分かり、単純承認をすると今住んでる自宅を出ていかなくてはいけなくなってしまうことがあります。
このような場合に限定承認をすれば、住んでいる自宅の価値の範囲内で借金を返済することで、その家に住み続けることができます。
手続きなどは煩雑になりますが、どうしても相続したい家や土地などがある場合、この方法がおすすめです。
手続きは相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請する必要があります。
【方法③】相続放棄
相続放棄とはその名の通り財産の相続を放棄することです。
まだ住宅ローンの残債が多いなど、残された財産に負債が多い場合は相続放棄を選びましょう。
こちらを選択すれば住宅ローンの支払い義務を免れることができます。
こちらも相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申請する必要があります。
住宅ローンの相続後、残債がある場合は任意売却を検討!
任意売却とは、住宅ローンを相続して負債が残ってしまった場合の対策法の1つです。
相場に近い価格で売却することができるため、残債を完済または少なくすることができます。
債務が残ったとしても、無理のない返済計画を立てられるパターンが多いので比較的負担が少なくなります。
任意売却は競売と違って、自分の都合で引き渡しや引っ越しの時期を決めることができるため、ある程度準備期間を設けることができます。
メリットの多い任意売却にも、もちろんデメリットはありますが、多くの人が任意売却を選ばれます。
不明点などがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
住宅ローンと相続についてのQ&A
住宅ローンと相続に関してよくいただくご質問は次の通りです。
1つずつ、分かりやすくご案内していきます。
Q.住宅ローンの相続手続きは、どのタイミングで行う?
相続発生時にやらなければならないことは、主に以下の通りです。
- 死亡届の提出
- 死亡保険金の請求手続き
- 年金や健康保険の手続き
- 各種料金の引き落とし口座の変更や解約
- 遺言の有無の確認
- 相続人確定
- 相続財産の把握
- 相続の選択(単純承認、限定承認、相続放棄)
- 被相続人の所得税の申告と納税
- 遺産分割
- 貯金や有価証券(株式、手形、小切手など)の解約及び名義変更
- 不動産の相続登記
- 相続税申告書の作成、申告、納税
たくさんやることがありますよね。
団信に加入している場合もそうでない場合も、相続の選択(相続が発生してから3ヶ月以内)までにどうするか決める必要があります。
相続人の確定には、被相続人の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本が必要です。
この取り寄せや相続人同士で連絡を取り合うことなどを考えると、実質はおよそ2ヶ月です。
団信未加入で住宅ローンなどのマイナスの財産が多い時は、家(不動産)を相続した人がそのまま残りの負債も相続します。
後回しにせず早めの手続きをおすすめします。
Q.相続が発生して住宅ローンが免除されるまでの流れは?
- 住宅ローン加入者が死亡(または高度障害)で相続が発生
- 相続人が住宅ローンを借りていた金融機関に加入者の死亡を伝える
- 加入者名義の口座を相続人の名義に変更する
- 金融機関から「団信弁済届」を受け取る
- 「団信弁済届」を記入し、金融機関に提出
- 保険金が降りるまでの審査があるため待機
- 団信から金融機関に保険金が支払われる
- 金融機関から完済証明書と抵当権抹消手続きの書類を受け取る
- 家(不動産)の所有者名義を相続人に買える
- 抵当権抹消の手続きを登記所で行う
相続が発生して住宅ローンが免除されるまでの流れには、10の手順があります。
特に大事なポイントについてご案内していきます。
相続発生時の対応
加入者が死亡(もしくは高度障害)した場合、相続の順位によって相続権が与えられる人が決まります。
あなたが相続人に該当する場合、まずは加入者が住宅ローンを借りてきた金融機関へ連絡をします。
そこで、加入者が亡くなったことを伝え、同時に加入者名義の口座を相続人の名義に変更しておきましょう。
その後、金融機関から「団信弁済届」という書類が渡されます。
必要事項を記入して提出したら、保険金の支払いについての審査が始まります。
団信の保険が支払われてから行うこと
完済したという証明書と抵当権抹消手続きの書類が金融機関から渡されます。
まずは家(不動産)の名義を1度相続人の名義に変更します。
それから抵当権抹消登記の申し立てを行いましょう。
この手続きは自分で行うか、司法書士など登記の専門家に依頼するかの2パターンに分かれます。
家(不動産)がある管轄の法務局へ行けば、書類の書き方なども教えてもらえます。
自分でも手続きは可能ですが、忙しい人やよりスムーズに終わらせたいという人は専門家に依頼することもおすすめです。
費用は5,000~10,000円程度です。
参考)住宅金融支援機構
Q.相続後、団信に加入していても一時的に住宅ローンを支払うことがある?
A.はい、あります。
団信の手続きに1~2ヶ月ほど時間がかかるので、この間の住宅ローンは支払い続ける必要があります。
ただし、保険金が支払われることが決定したら、この時支払った分は返金されるので安心して下さい。
保険金が支払われたら、住宅ローンの支払いは終了です。
Q.免除に気付かずに相続後に住宅ローンを支払い続けていた場合はどうなる?
A.加入者が死亡した後も住宅ローンを支払い続けていた場合、金融機関にその旨を申し出て下さい。
そうすれば返金されます。
相続が発生すると、片付けなどやることが多く忙しい日々を過ごさなければなりません。
住宅ローンの返済免除の手続きに着手できるまで、時間がかかることが予想されます。
金融機関に加入者の死亡を伝える際に、余分に支払った住宅ローンがある場合それを一緒に伝えて下さい。
Q.相続前の住宅ローンの手続きの際、団信に加入できないケースとは?
A.もともと持病がある場合、団信に加入できないというケースもあります。
団信に加入する際には告知事項があります。
- 過去3ヶ月以内に医師の治療や投薬を受けたか
- 過去3年以内に大きな病気に罹患したか
- 手足や身体の機能に障害があるか
告知の必要がある病気は以下の通りです。
| 病名 | |
|---|---|
| 心臓 | 狭心症、心筋梗塞、心筋症、不整脈、心臓弁膜症、先天性心臓病 |
| 脳 | 脳卒中(脳出血、脳梗塞、くも膜下出血)、脳動脈硬化症 |
| 呼吸器 | 慢性気管支炎、ぜんそく、気管支拡張症、肺結核、肺気腫 |
| 胃腸 | 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、膵臓炎、クローン病 |
| 肝臓 | 肝炎、肝硬変、肝機能障害 |
| 腎臓 | 腎炎、ネフローゼ、腎不全 |
| 目 | 緑内障、網膜・角膜の病気 |
| がん | がん、肉腫、白血病、腫瘍、ポリープ |
| 代謝異常・免疫疾患 | 高血圧症、糖尿病、貧血症、膠原病、リウマチ、紫斑病 |
| 精神疾患・認知障害 | 精神病、神経症、統合失調症、てんかん、うつ病、自律神経失調症、アルコール依存症、薬物依存症、知的障害、認知症 |
| 婦人科系 | 子宮筋腫、子宮内膜症、乳腺、卵巣嚢腫 |
「団信が無いと不安」という人は、加入条件が緩和されているワイド団信がありますので、それを取り扱っている金融機関を探してみて下さい。


![お電話での無料相談 [受付時間]9:00-18:00 女性相談員も応対します。](https://ninbai-japan.or.jp/wp/wp-content/themes/ninbai-japan/images/new/common/header_right_ttl.png)